一日一曲(1409)ブラッハー、ボリス:24の前奏曲
本日は、没後50年(1975年1月30日没)を迎えらえたドイツの作曲家、ボリス・ブラッハーさんの曲をご紹介します。
ブラッハーさんは1903年に当時の満州の街、牛庄镇(中国語:牛庄镇)で生まれました。両親はドイツ系のエストニア人でしたが、ロシア系でもあったようで、その関係で牛庄镇のロシア語圏に当時住んでいたとのことです。生まれてからの数年間は中国とロシアのアジア地域で過ごし、1919年にハルビンに落ち着きました。その後、1922年にベルリンに行き、最初は建築を数学を学びましが、方針転換、音楽の道を志し、ベルリン音楽大学で音楽を学びました。卒業後はポピュラー音楽や映画音楽のアレンジの仕事から始め、音楽院の教授職や作曲活動など幅広く活躍されました。ナチス時代には「堕落した音楽を書いた」として告発され、その結果ドレスデン音楽院での教職を失うというアクシデントに見舞われました。第二次世界大戦終了後に復権し、ベルリン芸術アカデミーの会長にまで上り詰めるなど、活躍されました。1975年1月30日にベルリンで72歳で亡くなられました。
本日の曲はピアノ曲集「24の前奏曲」です。本曲集も24の調性全てを使って創られています。曲の順番と調性、拍子を記します。
番 調 拍子
1 C 2/2
2 Bm 3 4 5 6 7 8/8
3 C# 3/4
4 B♭m 9/8
5 D 8 7 …4 3/8
6 Am 4/8
7 E♭ 5/4
8 G#m 6/8
9 E 1 2 3 4 5 8/8
10 Gm 7/8
11 F 4/4
12 F#m 13 8 5 3 2 1/8
13 G♭ 1 2 3 5 8 13/8
14 Fm 4/4
15 G 7/8
16 Em 8 5 3 2 1/8
17 A♭ 6/8
18 E♭m 5/4
19 A 4/8
20 Dm 1 2 3 4 5 8/8
21 B♭ 9/8
22 C#m 3/4
23 B 8 7 6 5 4 3/8
24 Cm 2/2
所々で表れる、変拍子が印象的です。各曲は1分前後ととても短く、全体での演奏時間も約19分となっています。
並び順に関してですが、曲集「24の前奏曲」の並び順でよくあるのが、ショパンのように五度圏を平行調ごとにめぐる配列(ハ長調ーイ短調ート長調ーホ短調ー・・・)や四度圏ではいれつしたもの、バッハのように半音ずつ同主調ごとに上昇する配列、などが一般的ですが、ブラッハ―さんは、
『奇数番の曲はドかラ始まって半音ずつ上昇していく長調、偶数番はシ(第1番のドの半音下)から始まって半音ずつ下降していく短調』
という、独自の配列となっています。
番 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
長調 C C# D E♭ E F G♭ G A♭ A B♭ B
番 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
短調 Bm B♭m Am G#m Gm F#m Fm Em E♭m Dm C#m Cm
短調
上の表を見ますと、どうせだったら、第3番は嬰ハ長調(C#、#7)ではなく変ニ長調(D♭、♭5)、第4番は変ロ短調(B♭m、♭5)ではなく嬰イ(A♯m、#7)、第18番は変ホ(E♭m、♭6)ではなく嬰ニ(D♯m、#6)、としたら、長調系はフラット記号、短調系はシャープ記号で統一できたのではないかと思ったのですが・・・。
第1番ではハ長調の音階をもじった旋律?が使われていましす。第1番は(ハ長調なので)基音ドで始まり、めぐりめぐってドに戻ってきた最終曲の第24番ハ短調では、第1番と似た形でハ短調の音階をもじった旋律が用いられています。この2曲は対になっていますね。拍子についても、1~12番と13~24番で対象になっているようです(12番と13番で折り返すと分かりやすいです)。他にもいろいろと仕掛けはありそうですが、これ以上は楽譜と格闘する必要がありそうです。
耳に心地よいかどうかは別として、面白い曲です。楽譜の最後には「12.4.1974」と印刷されています。ブラッハ―さんが亡くなられたのは1975年1月30日ですから、約2か月前の日付となります。もしかしたら本曲がブラッハ―さんの最後の曲だったのかもしれません。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ブラッハー、ボリス:24の前奏曲
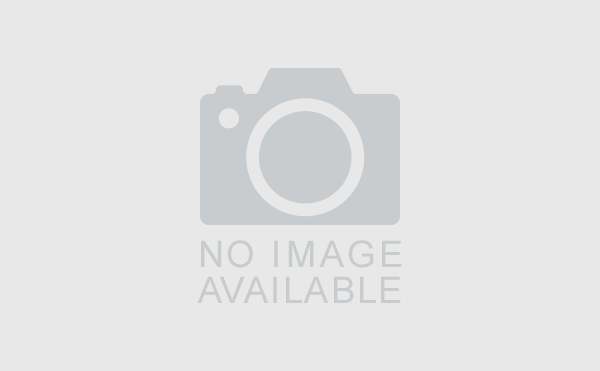
“一日一曲(1409)ブラッハー、ボリス:24の前奏曲” に対して1件のコメントがあります。