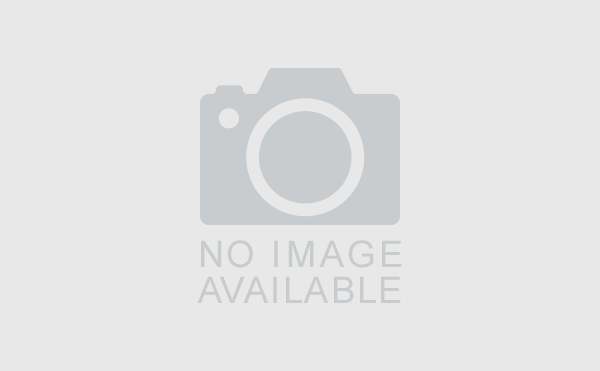一日一曲(1435)ソロタリョフ、ウラディスラフ:アコーディオンソナタ第3番より第4楽章
本日は、昨日ご紹介した作曲家ソロタリョフさんの作品を、もう一曲ご紹介します。
曲の紹介の前に、本日は「バヤン」について記します。「バヤン」とは『ロシアあるいはウクライナの民族楽器。俗にロシア式クロマティック・アコーディオンと呼ばれる。』が定義となります。簡単に言うと、アコーディオンの一種ということですね。アコーディオンにはピアノのような鍵盤式と簿ボタン式がありますが、バヤンはボタン式ということになります。バヤンでは、ボタン式アコーディオンのために書かれた作品はすべて演奏できるそうです。
バヤンは1907年にピョートル・ステリゴフによって発案され、バラライカとのアンサンブルの伴奏楽器として用いられてきました。イタリア式ボタンクロマティック・アコーディオンを参照して徹底的に構造が刷新され、1929年に原型が完成、メーカーに依ってはイタリア式を超える改造を施したものもあるそうです。オーケストラの定石楽器は長年ハーモニウムだったのですが、多くのメーカーが倒産するという歴史を経て、アコーディオンがその席を奪う形になったそうです。なお、バヤンは出自の関係で、ロシアやウクライナ以外の音楽学校では「バヤン科」が存在しない、とのことです。
本日は、昨日ご紹介したバヤン奏者兼作曲家、ソロタリョフさんの「アコーディオンソナタ第3番」です。残念ながらNMLには終楽章(第4楽章)(NMLでは第6楽章となっていますが、これは間違いです。YOUTUBEのスコア付きの演奏のリンクを参照してください。13分38秒から第4楽章が始まります。楽譜に「Ⅳ」としっかり表示されています。余談ですが、NMLでは、ちょこちょここう言ったミスが見られます。)の演奏しかありませんでした。
・・・と、探していたら、YOUTUBEで全曲の演奏を、しかも楽譜付きで見つけましたので、こちらも挙げておきます。
第4楽章では重要な引用が2つあります。
一つは、グレゴリオ聖歌の「怒りの日」の旋律。NMLでは1分50秒から、YOUTUBEでは15分22秒からの部分です。かなり特徴のあるメロディなので、特に書かれた解説などを見つけたわけではないのですが、聴いていて分かりやすい引用でした。
二つ目はシェーンベルクの「浄夜」からの引用。シェーンベルクが同曲の中で、登場人物の一人である女性が男性に向かって「罪」を告白し、告白を終えて男性の返答を待ち、男性が女性に応える場面を描写しているのですが、それがアコーディオンでそっくりそのまま再現されます。この部分は前半非常に重苦しく、後半は男性の応答が「罪の赦し」のように温かく包み込むような、救いが本当にここに実現したというような、そんな雰囲気の音楽が奏でられています。男性の「赦し」の言葉の部分で、救われるように、悲鳴にも似た不協和音の咆哮の激情迸る音楽が、平和な光の内に終了します。この引用部分は約4分間。第4楽章全体の半分近くとなっています。シェーンベルクを尊敬していたソロタリョフさんが、その中でも印象深い、恐らく大好きな曲の大好きな部分を借用したのではないでしょうか。本曲の終了部のような安らぎ、平和な時間をソロタリョフさんはどれほど渇望していたのか、その想いがひしひしと伝わってきます。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ソロタリョフ、ウラディスラフ:アコーディオンソナタ第3番より第4楽章
ソロタリョフ、ウラディスラフ:アコーディオンソナタ第3番より第4楽章(MP3ダウンロード)
ソロタリョフ、ウラディスラフ:アコーディオンソナタ第3番(YOUTUBE)