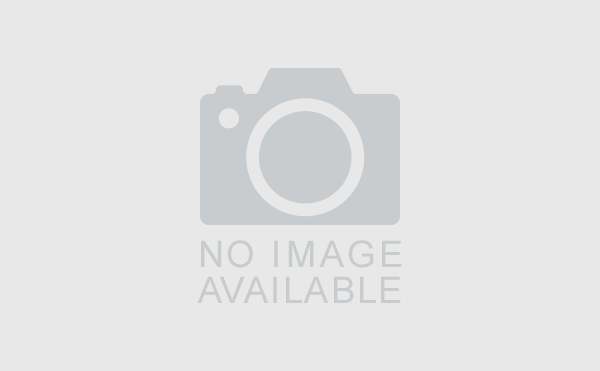一日一曲(1582)ヘムシ、アルベルト:ピルプール・ソナタ
本日は、没後50年(1975年10月8日没)を迎えらえたトルコ生まれのユダヤ系作曲家、アルベルト・ヘムシさんの曲をご紹介します。
ヘムシさんは、1898年6月にトルコのイズミル近郊の街カスタバで生まれました。イタリアのミラノ音楽院で作曲や指揮を学びました。イタリア滞在中に第1次世界大戦となり、徴兵されてしまいます。戦争の終わりには大尉にまで昇進しますが、戦闘の中で右腕の筋肉に重大かつ永久的な損傷を負い、ピアニストとしてのキャリアという目標を追求することができなくなってしまいました。その後、イタリアから故郷に戻り、スマーナで理論、ピアノ、合唱を教えました。1924年、ロードス島のイタリア領事館で通訳の職に就きました、そこで妻のミリアムと出会いました。1927年にエジプトのアレクサンドリアのエリヤフ・ハナヴィ・シナゴーグで音楽監督兼合唱団の指揮者として働きました。第二次大戦後はイスラエルを経てフランスに定住し、創作と研究を続けました。若くして地中海各地に伝わるセファルディ民謡の収集に情熱を注ぎ、その旋律を芸術作品へ昇華させた点が彼の特徴です。代表作「Coplas Sefardies」などで民俗的素材を声楽や室内楽に取り入れ、民族音楽学的価値と芸術的完成度を兼ね備えました。。ヴァイオリンとピアノのための「Pilpúl Sonata, Op.27」(1942)は、ユダヤ的伝統の精神と西洋的形式を融合した代表作の一つです。1975年にパリで没し、セファルディ文化の伝承者として記憶されています。
本日の曲は、その代表作「ピルプール・ソナタ」です。3楽章形式のヴァイオリンとピアノのためのソナタで、演奏時間は約20分です。
「ピルプール(Pilpúl)」というタイトルは、ヘブライ語/ユダヤ教伝統の概念に由来しています。具体的には:pilpúl(ヘブライ語: פִּלפּּוּל/pilpul)はユダヤ教における タルムード研究の一形式 を指し、一種の細かい議論、解釈の論争、入念な論理的討議を伴う方式を意味します。言い換えれば、細部を突き詰めて議論する、詭弁的・論争的・議論を楽しむような学びの伝統が背景にあります。ヘムシさんはこの「pilpul」という概念を、音楽的・形式的にも取り入れようとしており、第1楽章のような軽快な対話性、即興感、応答のやりとり、変化するリズムなどが、この「議論する」「突き詰める」という性質とリンクすると評価されています。「Pilpúl Sonata」というタイトルは、単にユダヤ的・民族的なイメージを呼び起こすものというだけでなく、学問的・議論的な精神、細部への注意、対話(instrumental dialogue)と変化を重視する作風を示すキーワードとして機能しています。音楽がまるで「論争を交わす」かのような構造(応答、反復、装飾、変奏など)が含まれている、という見方が可能です。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ヘムシ、アルベルト:ピルプール・ソナタ
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc9e2b9.12be46d5.4cc9e2ba.1c90c083/?me_id=1251035&item_id=25906513&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2Fa32%2F40000%2F13239213.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)