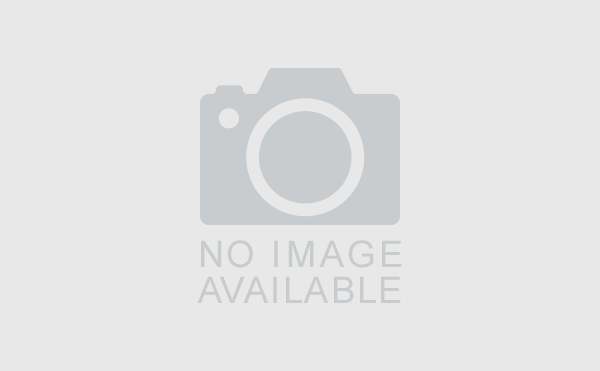一日一曲(1630)パレストリーナ、ジョヴァンニ・ダ:アヴェ・マリア
本日は、生誕400年(1525年生)を迎えらえたイタリアの作曲家、ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナさんの曲をご紹介します。
パレストリーナさんは当時はローマ教皇領であったローマ近郊の町、パレストリーナで生まれました。一般に「パレストリーナ」と呼ばれているのですが、実は「ジョヴァンニ・ピエルルイージ」が名(ファーストネーム)で、「ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ」とは「パレストリーナ出身のジョヴァンニ・ピエルルイージ」という意味あいとのことです。1537年のサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂の聖歌隊員名簿に名前が載っており、このときはじめてローマに来たものと考えられています。1544年から1551年にかけて、郷里で最も大きなサンタ・ガーピト大聖堂のオルガン奏者を務められました。また、作品を初めて出版もされています。出版した「ミサ曲集」は、同時代のイタリアで宗教音楽を作曲した作曲家の出身がネーデルラント、フランドル、フランスかイベリア半島で占められていた中で、初めてのイタリア半島出身者が出版したものとなりました。1550年にはジュリア聖歌隊の楽長を指す「マエストロ・ディ・カペッラ」に任命されました。ところが、パウルス4世の時代(1555年-1559年)に入ると状況が変化します。パウルス4世はカトリック教会の改革を目指した厳格な教皇であり、パレストリーナさんは既婚者であったという教義上の理由により、他の同様の音楽家とともに解雇されてしまいました。その後の15年ほどの間、パレストリーナさんは、ローマにある他のいくつかの教会で楽長を務められましたた。有名なところでは、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂(1555年–1560年)と、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂(1561年–1566年)です。パウルス4世が亡くなると教義的障碍も無くなり、1571年にはまたサン・ピエトロ大聖堂に呼び戻され、以降生涯そこを離れることがありませんでした。1570年代の10年間は身内に不幸が続きました。弟、音楽家として成長していた二人の息子、そして妻を、それぞれ1572年、1575年、1580年のペストの大流行で失いました。パレストリーナさんは失意に陥り、一時期は僧侶になることも考えたようなのですが、紆余曲折の末、裕福な毛皮商の未亡人と再婚しました。そのため経済的な独立を得ることができ(聖歌隊の楽長としての給料は不十分なものだった)、亡くなるまで生活に困ることなく作曲し続けることができたとのことです。1577年には、当時の教皇からグレゴリオ聖歌の改革を命じられました。1594年に胸膜炎で亡くなられました。少なくとも100以上のミサ曲、250以上のモテトを初めとする数多くの教会音楽を作曲したことから、「教会音楽の父」ともいわれています。
本日の曲は合唱曲「アヴェ・マリア」です。本ブログでは他の作曲家の同名の作品をかなりご紹介してきていますが、その中でも本曲は人気のある作品ではないでしょうか。厳かな響きが印象的です。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
パレストリーナ、ジョヴァンニ・ダ:アヴェ・マリア
パレストリーナ、ジョヴァンニ・ダ:アヴェ・マリア(MP3ダウンロード)
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ddcd78e.5614046c.4ddcd78f.0ade2323/?me_id=1213310&item_id=21759257&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3803%2F4260052383803.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)