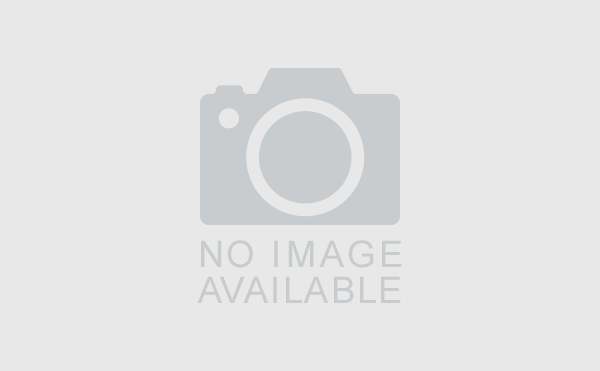一日一曲(1097)デュボワ、テオドール:ヴァイオリンソナタ イ長調
本日は、没後100年(1924年6月11日没)を迎えらえたフランスの作曲家、テオドール・デュボワさんの曲をご紹介します。
デュボワさんは1837年にフランス北部のランス近郊のマルヌ村ロズネーで生まれました。1854年にパリ音楽院に入学し、ピアノ、オルガン、和声、対位法、作曲を学びました。和声、フーガ、オルガンで連続して一等賞を獲得、1861年には、フランスの最高の音楽賞であるローマ賞を獲得しています。その後ローマを中心にイタリアで研鑽を重ね、1866年に帰国、サント・クロチルドの聖歌隊指揮者に任命され、華やかなキャリアがスタートしました。1871年には国立音楽協会設立時には創設メンバーに名を連ねました。 同年、パリ音楽院の教授に任命され、以後20年間和声学や作曲を教えました。さらに1896年には院長に昇進されています。かなり保守的な教育方針であったため、革新的な学生たちとは対立する形となってしまいました。1905年に後に大作曲家となるラヴェルがローマ賞に挑戦した時に、彼の優勝を阻止しようと露骨な動きを起こした中心人物であり、そのことが引退を早めることとなってしまいました。引退後もパリ音楽院の同窓会長など活発に活動されていましたが、1924年に86歳で亡くなられました。
本日の曲は「ヴァイオリンソナタ イ長調」です。「ヴァイオリンソナタ イ長調」と言いますと、同じフランスの作曲家フランクさんの名曲がありますので、その陰にすっぽりと隠れてしまっていますが、本曲もなかなか魅力的です。フランクの陰に隠れてしまったのが不運でした。技巧よりも、ヴァイオリンを美しく響かせることに軸足を置いた曲の作りとなっています。第1楽章の出だし、重音で入ってくるヴァイオリンが印象的です。明るく伸びやかなメロディが心地よく耳に響きます。穏やかな第2楽章を挟んで少し激しい感情のほとばしりが現れる第3楽章、そして最後はフランクのソナタと同じように第1楽章の主題が戻ってくる「循環形式」で曲が締められます。
もう少し演奏される機会が増えても良い曲だと感じます。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
デュボワ、テオドール:ヴァイオリンソナタ イ長調