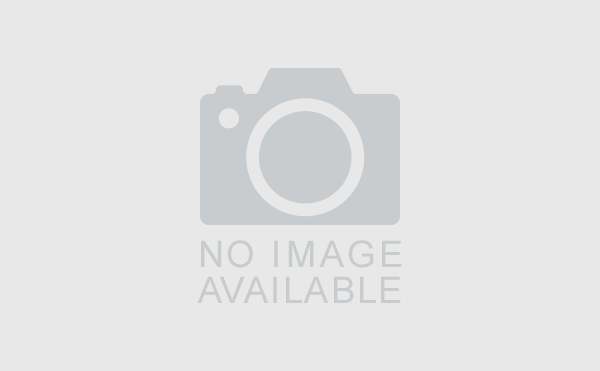一日一曲(1110)ミヨー、ダリウス:交響的組曲第2番
本日は、没後50年(1974年6月22日没)を迎えらえたフランスの作曲家、ダリウス・ミヨーさん特集の2回目です。
1914年に第一次世界大戦が始まりました。ミヨーさんは健康上の理由で従軍することができませんでした。愛国心からか、戦争に関わることのできる仕事を探し、「フランス・ベルギー親善協会」]に勤務することとなったそうです。ただ、一年後にはその職を辞し、外交官秘書となり、1917年から1918年末まではブラジルに赴任しました。この地でブラジルの音学区に強く影響されることとなります。その成果は『ブラジルへの郷愁』『屋根の上の牛』などの作品にあらわれてています。ミヨーさんがブラジルに滞在していた間、パリではバレエ・リュスの『パラード』の初演(1917年5月)がスキャンダルを引き起こし、ミヨーと既知のオネゲル、タイユフェール、オーリックなど若手作曲家は、エリック・サティ、ジャン・コクトーを中心として結集しつつあった。ブラジルから帰国したミヨーさんもその一員となり、彼らは毎週土曜日にミヨーさんの自宅に集まって友情を育まれたそうです。こうして、デュレ、オネゲル、タイユフェール、プーランク、オーリック、そしてミヨーさんの「フランス6人組」が結集されることとなりました。
1919年10月24日、12種類の調性が同時に鳴る部分を含む『交響的組曲第2番』(付随音楽『プロテー』に基づく)が初演されました。この演奏会は聴衆の猛反発を招き、混乱した会場に警察や市警備隊が介入、新聞に「コンセール・コロンヌのスキャンダル」として報じられる事態となってしまいました。けれどもミヨーさんは「熱狂でなくても強い抗議は作品によって刺激されている証拠」であるとして意に介さず、かえって自信を深めた、とのことです。
本日はその「交響的組曲第2番」をご紹介します。通して聴きましたが、そこまで反発を受けるような曲なのかな?というのが第一印象です。普通にきれいな曲です。「12種類の調性が同時に鳴る部分」がどこなのか、調べたのですが、ちょっとわかりませんでした。5曲からなる組曲で、演奏時間は約20分。4曲目はミヨーさん自身によりヴァイオリンとピアノの小品「春」作品18に編曲されています。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ミヨー、ダリウス:交響的組曲第2番