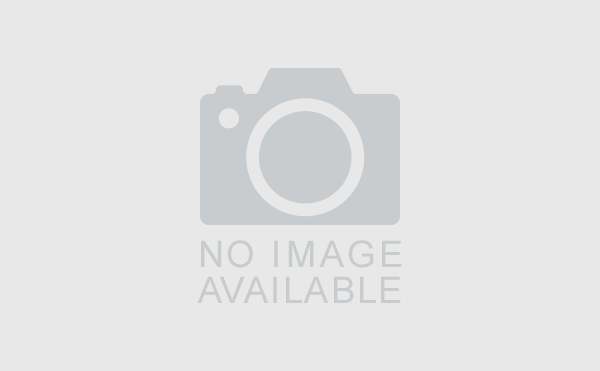一日一曲(1522)ショスタコーヴィチ、ドミートリー:歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」
本日から5回にわたって、没後50年(1975年8月9日没)を迎えらえたロシアの作曲家、ドミートリー・ショスタコーヴィチさんを特集いたします。
ショスタコーヴィチさん1906年9月にロシア帝国の首都であったサンクトペテルブルクで生まれました。両親が音楽好きなこともあり、ショスタコーヴィチさんは小さい頃から声楽やピアノなどに親しむなど、音楽に接する時間に恵まれた幼少期を過ごしました。母のすすめでピアノを演奏するようになるとまたたく間に上達し、ハイドンの交響曲の緩徐楽章やショパンなどを演奏するようになりました。サンクトペテルブルクのグリャスセル音楽学校でピアノと作曲を学び、1919年にはペテルブルク音楽院(後にペトログラード音楽院、レニングラード音楽院)に入学。在学中の1925年に音楽院作曲科の卒業作品として作曲された交響曲第1番において国際的に注目されることとなりました。ただし、その後の道のりは平たんではありませんでした。1928年に作曲されたオペラ「鼻」は、劇場の歌手からの反発で頓挫してしまいました。1931年、ショスタコーヴィチさんは雑誌『労働者と演劇』にて「作曲家の職務宣言」と題した論文を発表し、プロパガンダ的な制約のある音楽制作を求めるプロレタリア音楽家協会を批判しました。この論文は当初、プロレタリア派の作曲家たちからの反論を受けましたが、1932年4月23日から25日にかけて行われた作曲家会議では、逆にプロレタリア音楽家協会が批判を受け、翌日公布された党中央委員会決議「文学・芸術組織の再構築について」にてプロレタリア音楽家協会をはじめとする同様の組織は解体となり、この対決はショスタコーヴィチさんの勝利に終わりました。1934年、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」で大成功を収め、それがきっかけとなりレニングラード市の代議員も務めるようになりました。順風満帆でしたが、1936年1月に運命は暗転します。話題作「ムツェンスク郡のマクベス夫人」を観劇したソビエトの最高権力者ヨシフ・スターリンは、上演の途中で席を後にしてしまいます。その2日後、ソヴィエト共産党機関紙『プラウダ』にて「音楽の代わりの支離滅裂 オペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」について」と題された匿名の論文が掲載されることとなりました。これが有名な「プラウダ批判」です。
本日の曲は、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」です。今回は少々長いですが、全曲盤を挙げておきます。言葉の意味が分からないで聴いていますが、そこまで非難されるような音楽かな?と感じます。今回は何か書けるほど聴き込んではいませんので、これで失礼します。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ショスタコーヴィチ、ドミートリー:歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」