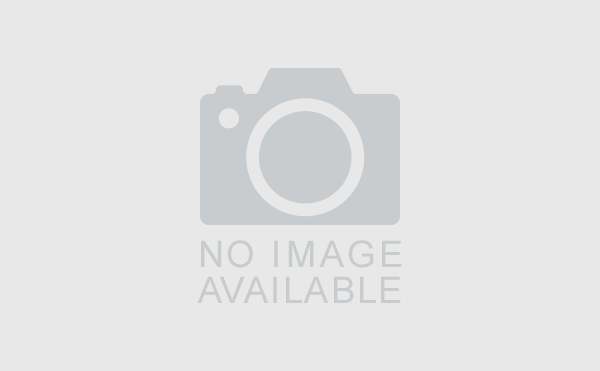一日一曲(1524)ショスタコーヴィチ、ドミートリー:交響曲第10番ホ短調
本日は、没後50年(1975年8月9日没)を迎えらえたロシアの作曲家、ドミートリー・ショスタコーヴィチさん特集の3回目です。
全世界が戦争の時代に突入する中、ソ連もこの渦の中に巻き込まれます。1941年には独ソ戦が、同年9月からはレニングラード包囲戦が始まりました。ショスタコーヴィチさんは戦火真っただ中のレニングラードの市民を鼓舞するため交響曲第7番「レニングラード」を作曲します。本曲は大成功を収めることとなりました。続けてショスタコーヴィチさんは交響曲第8番を作曲します。この第8番は、戦いへの勝利を描いた第7番とは対照的に、戦争の惨禍や犠牲者を偲ぶ重く深刻な内容でした。すぐに当局からの批判の対象となり、交響曲第8番はあっという間にレパートリーから外されてしまいました。ショスタコーヴィチさんは更に続けて交響曲第9番を発表します。この曲はナチスへの勝利が決定的となった1944年に書かれた作品で、戦争の勝利を祝う内容の作品でした。ところが、軽快さにあふれる第9番は、またしても当局の不興を買ってしまいます。当局はベートーヴェンの交響曲第9番のような壮大で賛美的な内容を期待しており、それを裏切る結果となってしまったののです。発表後は、第8番同様激しい批判にさらされました。戦後も当局の芸術への介入は続き、1948年には悪名高い「ジダーノフ批判」が発表されます。この批判の中では、ソビエトの作曲家のほとんどが「形式主義者」として共産党により批判されました。このピンチに、ショスタコーヴィチさんは、オラトリオ『森の歌』、映画音楽『ベルリン陥落』、カンタータ『我が祖国に太陽は輝く』など、あからさまに当局に迎合した共産党賛美の作品を矢継ぎ早に発表します。これらの曲により、ショスタコーヴィチさんはなんとか名誉回復を勝ち得ることが出来ました。1953年にスターリンが死ぬと、発表を控えていた作品を多数公開したほか、約8b年ぶりに新曲の交響曲(第10番)を発表しました。この曲は内容の暗さと「社会主義リアリズム」との関係において、大論争(いわゆる第10論争)を巻き起こし、国外でも大きく報道されました。
本日はその「交響曲第10番ホ短調」をご紹介します。
ソビエトの楽壇では、この曲の評価に関して賛否両論に真っ二つに分かれてしまい、3日間に渡る討論会が行われた、とのことです。なお、ショスタコーヴィチさん自身は「この作品は欠点が多いがそれでも可愛いものだ」と余裕の発言を残していらっしゃるそうです。
本交響曲は、大指揮者カラヤンが録音した唯一のショスタコーヴィチ作品でもあるそうです。カラヤンはショスタコーヴィチさんに親近感を抱いており「私は作曲をしないが、もししたとしたらこのような曲を書いただろう」と語っていらっしゃいます。この作品の演奏によほどの自信があったようで、1969年のソビエト公演の際、ショスタコーヴィチさんとソヴィエトの誇る大指揮者ムラヴィンスキーの前で演奏しています。この時、ショスタコーヴィチさんは「こんなに美しく演奏されたのは初めてです」と評価したそうです。ただ、これが褒め言葉なのかは分からないとのことです。
本日は、カラヤンさんが作曲者自身に聴かせた時のライブ録音盤でどうぞ。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ショスタコーヴィチ、ドミートリー:交響曲第10番ホ短調