一日一曲(1386)ブーレーズ、ピエール:ピアノソナタ第3番
本日は、生誕100年(1925年3月26日生)を迎えらえたフランスの作曲家兼指揮者、ピエール・ブーレーズさんの曲をご紹介します。
ブーレーズさんはフランス中南部の街モンブリゾンで生まれました。パリ国立高等音楽院でアンドレ・ヴォラブール(アルテュール・オネゲルの妻)とオリヴィエ・メシアンに対位法や作曲を学びましたが、音楽院を中退、その後、ルネ・レイボヴィッツから現代音楽の作曲技法のひとつ、セリアリスムを学びました。ダルムシュタット夏季現代音楽講習会でその初期から活躍し、注目されるようになりました。作曲の中には「偶然性」も取り入れましたが、「管理された偶然性」を提唱、偶然性の結果によってどんなに音楽が異なる解釈をされようとも、全体としては作曲者の意図の範囲で統率されるべきとしました。この考えに基づく作品として「ピアノソナタ第3番」、『プリ・スロン・プリ – マラルメの肖像』などが挙げられます。フランス国立音響音楽研究所IRCAMの創立者で初代所長として活躍されました。1992年の所長退任後は名誉総裁に就任されています。1976年、コレージュ・ド・フランス教授に選出されています。指揮者としてもニューヨーク・フィルハーモニック音楽監督などの重要ポストに就き、華々しく活躍されました。2009年、京都賞受賞の際に催されたトークイベント(京都日仏学館)において、聴衆の一人から「人生における普遍的なあるべき考え方」を問われたところ、ブーレーズは「好奇心を持ち続けること」と述べています。2016年1月5日、バーデン=バーデンの自宅で90歳で死去されました。
本日は、上野文中で登場した「ピアノソナタ第3番」をどうぞ。
この曲は、アンティフォニー、トロープ、コンステラシオン、ストローフ、ゼクエンツの5つのフォルマン(形成されつつあるもの)から構成されています。この5つのフォルマンの演奏順序は演奏者に任されていますが、全くの無秩序なのではなく、必ずコンステラシオンが中心でなければならないとのことです。ブーレーズさんはこう語られています。「興味の中心は1つの作品の2つの顔を比較するなどということではなく、まさに作品が決して決定的に固定された1つの顔を持たないであろう、ということを知ることなのです。」
上の解説も、楽譜や資料を見ながら出ないと、なかなか素人には鑑賞は難しいかもしれません。私も、今回の演奏、どこがコンステラシオンなのか、まったくもって分かりません…。
作曲者自身の演奏です。ブーレーズさんは作曲家の他、指揮者としても高名でしたが、ピアノ演奏も仲奈々の腕だということが本曲の演奏で分かりますね。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ブーレーズ、ピエール:ピアノソナタ第3番
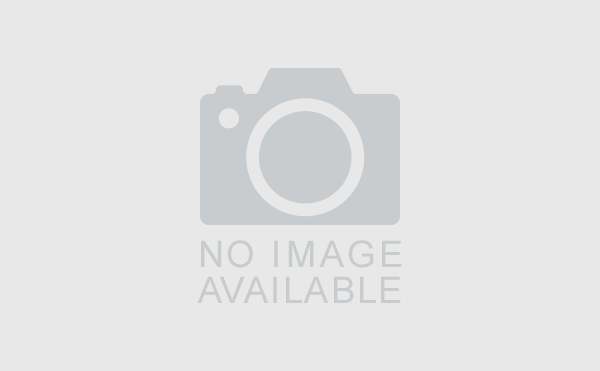
“一日一曲(1386)ブーレーズ、ピエール:ピアノソナタ第3番” に対して1件のコメントがあります。