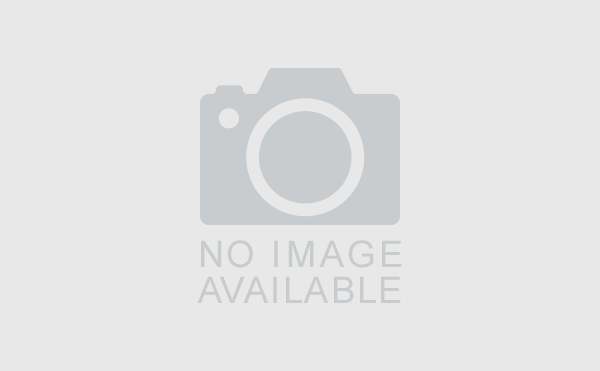一日一曲(1584)ボルトニャンスキー、ドミートリー:アヴェ・マリア
本日は、没後200年(1825年10月10日没)を迎えらえたウクライナ出身の作曲家、ドミートリー・ボルトニャンスキーさんの曲をご紹介します。
ボルトニャンスキーさんは1751年10月に当時のロシア帝国(現在のウクライナ、スムイ州フルヒフ)で生まれました。7歳のときに地元の教会の聖歌隊で驚異的な才能を発揮し、帝国の首都サンクトペテルブルクに移り、帝国礼拝堂聖歌隊に加わる機会を得ました。そこで作曲など音楽の基礎を学び、1769年に、師匠ガルッピとともにイタリアに行きました。イタリアでは、ヴェネツィアでのクレオンテ(1776年)とアルシド(1778年)、モデナでのクイント・ファビオ(1779年)などのオペラの作曲で大きな成功を収めました。また、ラテン語とドイツ語で、アカペラとオーケストラ伴奏の両方で、2つの声とオーケストラのためのアヴェマリアを含む神聖な作品を作曲しました。1779年にサンクトペテルブルク宮廷アカペラに戻り、少なくとも4つのオペラを作曲しました。また、この時期にピアノソナタ、ハープによるピアノ五重奏曲、フランス歌のサイクルなど、多くの器楽作品を書きました。さらに、東ヨーロッパと西ヨーロッパのスタイルの神聖な音楽を組み合わせ、イタリアで学んだポリフォニーを取り入れて、東方正教会のために典礼音楽を作曲しました。1796年には、ロシア帝国初の指揮者である帝国礼拝堂合唱団の指揮者に任命され、活躍されました。100以上の宗教作品、神聖な協奏曲(4部構成の混声合唱団で35曲、二重合唱で10曲)、カンタータ、賛美歌など、数十曲の楽曲を生み出しました。1825年10月にサンクトペテルブルクで亡くなられました。
本日の曲は「アヴェ・マリア」です。室内楽の伴奏付き、三楽章形式という、他の同名曲とは規模がかなり大きな作品です。演奏時間も約10分と、他の同名曲の3倍程度の長さです3つの楽章は、どれもゆったりとしたテンポの指定となっています。まあ、快活な「アヴェ・マリア」というのは、ちょっとイメージがつかないですので、妥当なところとは思います。が、曲としては、ちょっとのぺらっとしてしまっているような気がしないでもないです。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリ)より(NML会員以外の方でも無料で試聴できます)
ボルトニャンスキー、ドミートリー:アヴェ・マリア
ボルトニャンスキー、ドミートリー:アヴェ・マリア(MP3ダウンロード)
(ボルトニャンスキーさんの他のCD)
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cca6cd9.78278abd.4cca6cda.4fa6314a/?me_id=1431904&item_id=10491461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frecordcity%2Fcabinet%2Fracoon_120%2F2943044m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)